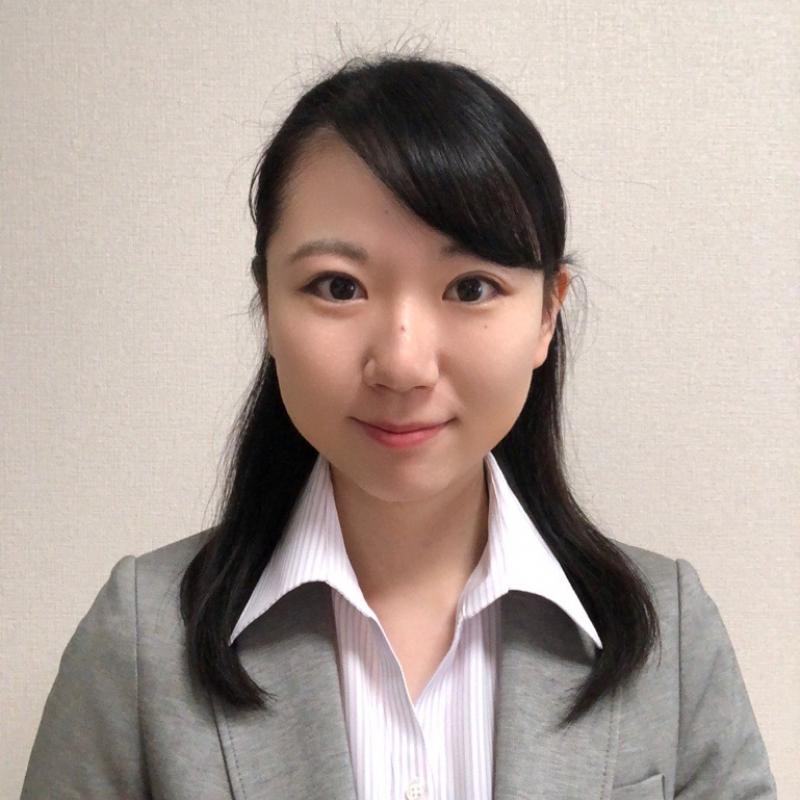「随分と寂しい街だな」― 2017年に私が旅行で訪れたベルリンは、ひどく霞んでいて、どこか歴史に囚われているように見えた。ベルリンの壁は、強い雨に打ち付けられながら、悲しい歴史を恨むかのように、静かにそこに佇んでいる。「暗さ」という意味では、今回のフォーラムのテーマ「高齢化」も同じである。実際、「老」という漢字は、腰の曲がった老人が杖をついている様子が成り立ちだそうだ。老いることは、杖に頼らなければ立つことも出来ないこと、生きる元気やエネルギーをだんだんと失うこと。私の中では、そういったマイナスのイメージに満ちていた。
こうした私の見方は、日独ヤングリーダーズ・フォーラムの10日間で大きく変わることになる。本稿を以って、フォーラムに参加した私の所感をご紹介したい。
未来の社会を形作る

社会の少子高齢化は、日独共通の課題だ。この解を探るべく、2023年秋、2020年以来コロナの終息を待ちわびた14名のヤングリーダーズがベルリンに集まった。日独それぞれの参加者のバックグラウンドは、政府関係者、研究者、企業関係者、起業家など、実に多様である。
参加者は、少子高齢化の課題について、年金制度、労働市場、移民等、様々な観点から検討した。議論は驚くほど活発で、教授の講演後には数多くの質問が飛び交ったばかりか、コーヒーブレイクの間も白熱した。日独双方の参加者の英語力は極めて高く、積極的に議論に貢献する姿勢に、私も大変刺激を受けた。目まぐるしい勢いで会話が展開され、議論の焦点が常に移り変わる中で、今この瞬間に私が発するべき言葉は何かを考え、要点を捉えて短く纏める必要がある。ここで求められるものは、もはや英語力というよりも、瞬発力や要約力と表現すべきかもしれない。
また、違うと思うことを違うとはっきり言う必要性も再認識した。参加者は、3~4名のワーキンググループに分かれ、各々のテーマに沿った、30分の最終プレゼンテーションを用意する。私の担当テーマは、「日独の年金制度における世代間・世代内の不平等とその是正」。プレゼンに説得力を持たせるべく、論理展開や引用すべきデータなどについて、3人でみっちりと議論した。

「世代間の金銭格差を比較するにあたって、インフレ率を考慮しないのはおかしい」。数学や経済に疎い私に対し、ドイツ側参加者は真っ向から反論した。その内容は至極尤もで、違うと思うことを躊躇せずに「違う」と言う姿勢は実に清々しく、同じチームにいてくれて頼もしいと思った。
「日本人は…」と括って主語にするべきではないと思うが、一般的に言って、人に反論することを躊躇う傾向にあると思う。これは、日本人の「和」を重んじる精神と関係するようだ。日本は、かつて「大和の国」とも呼ばれていたわけだが、ここにある「和」は、調和・和平・和解…の「和」。つまりはハーモナイゼーションである。調和を重んじるばかりに、「人がせっかく出した意見に反論しては申し訳ない」「相手との関係を崩してしまうのではないか」と心配する人が比較的多いように思う。和の心は議論の場でマイナスにばかり働くわけではないにしても、違うと思うことを面と向かって違うと言うそのドイツ人参加者の議論の仕方が、私は非常に好きだった。それは一緒により良いものを作ろうとする姿勢そのものである。最終プレゼンでは、本当に困っている人を救うために、両国においてどのような年金制度改革が必要か、具体論にまで踏み込んで発表することが出来たと思う。
他にも、移民や女性も働きやすい社会を作るために何が出来るか、高齢者も含め皆が生きやすい社会とはどのようなものかなど、少子高齢化について、様々な切り口で議論を重ねた。同じ課題を抱える日独だが、労働市場やテクノロジーの活用など、両国の対応状況は異なっており、互いから学べる余地は非常に大きい。こうした議論は、私が想定していた以上に、前向きなトーンで繰り広げられ、会議室はポジティブなエネルギーで満ちていた。少子高齢化社会を考えることは、老いを憂うことでも、過去の対応を嘆くことでもない。自分が将来生きる社会の像を各々が考えること、そして、状況を単に受け入れるのではなく、あるべき世界を形作っていくことなのだと気付かされた。この難しい課題を前に、ヤングリーダーズたる私たちが起こすべきアクションはたくさんある。
過去から学ぶ
会議室での活発な議論は私の老いへのイメージをがらりと変えたが、冒頭の「ベルリンの暗さ」を払拭したのは、街歩きである。毎日の会合場所への移動の間など、ちょっとした時間のおしゃべりは、私にとって発見の連続であった。例えば、私が「ベルリンでは州旗や熊をよく見かけるのに、ドイツ国旗は見かけないね」と呟くと、ドイツ側参加者は、ドイツ国旗は戦争を想起させるため滅多に掲げないこと、そしてその代わりに州旗が多用されていることを説明してくれた。また、ドイツ側の同窓生は、「ドイツ国旗を堂々と掲げた2006年のFIFAワールドカップは、なかなかに新しい経験だった」と熱を帯びた様子で語ってくれた。

国旗をあまり掲げないという点で日独は似ているかもしれないが、歴史に対するアプローチには、両国でかなりの違いがあると感じる。ベルリンの街を歩いていると、日常生活の中に歴史の面影が強く感じられた。道路のあちらこちらには金色のタイルのようなものが埋められている。今回の滞在中だけでもかなりの数を見かけたが、これは、第二次世界大戦中に迫害を受けたユダヤ人の慰霊碑だそうだ。また、美しいシュプレー川のすぐ傍には、東西ドイツの国境検問所Tränenpalastがある。日本語訳は、「涙の宮殿」。突如として現れたベルリンの壁に引き裂かれた家族や友人、恋人達が、この場所でたくさんの涙を流したことからこう呼ばれているそうだ。
悲しい過去の足跡は第二次世界大戦にまつわるものばかりではない。滞在したホテルのすぐ近くの教会前には、数枚の写真と花が並べられていた。2016年、クリスマスマーケットに大型のトラックが突入したテロ事件の犠牲者である。また、道路の脇に目をやると、自転車の死亡事故が起きた場所に置かれるという白い自転車が寂しそうにこちらを見ていた。
日本にも戦争を伝える博物館はあるが、日常生活の中でこれほどまでに歴史を想起させられることはないように思う。歴史教育についても、ドイツでは、幼い時から、日本で言う道徳と組み合わせる形で、歴史を議論しながら学ぶという。学生時代、歴史を暗記科目のように捉えていた私からすれば、この教育方法の違いは驚きだ。「どうしてこうも違うのだろう」と首を捻る私に、ドイツ側参加者の一人は、「敗戦後、日本はアメリカの指導のもと、焼け野原から立ち上がるエネルギーを経済活動に注ぐべく円陣を組めたが、東西ドイツは、歴史を繰り返さないという姿勢を各々明示的に示すことで、どちらが新しい国の首都に相応しいかを競う必要があったからではないか」と所感を共有してくれた。戦争の歴史はあまりにも残酷で、目を背けたくなるものだ。実際、ドイツ側参加者との会話がなければ、2017年の旅行者の私のように「ベルリンの街はなんだか寂しいな」の一言で終わってしまっていたかもしれない。日常生活に見え隠れする歴史の面影は、悲しい過去を繰り返さないという強い意志の表れであり、将来のために決して霞ませるべきではない教訓そのものである。
包摂する
移動中の車内、ドイツ側参加者が、あまりにじっと私の目を見て話を聞くので、私は話し終わる前に何だか笑えてきてしまった。私は笑いながら「本当に相槌を打たないよね」と言うと、彼も笑って「笑う時に口を手で覆う仕草も、なかなかシャイな感じでユニークだよ」と言った。
私の中に染み付いた些細な仕草は、日本国内ではなかなか意識しない。寝食を共にし、かなりの時間会話したからこそ、お互いに気付くことも多く、日独の参加者同士で仕草をからかい合うのが楽しかった。日本側の「へぇ~!」という相槌は、終盤には、ドイツ側参加者もネイティブさながらの完璧なトーンとタイミングで使いこなしていた。「今はドイツにいて英語で話しているんだから、あんまり相槌を打ちすぎないようにしなきゃ」と言う私に、ドイツ側参加者の一人が応えた。「自分は自分。習慣を無理に変える必要はないよ。大事なのは、それが習慣だと相手に分かってもらうこと」。この言葉に、はっとした。今まで少しは留学も経験し、文化の違いには慣れてきたつもりだったが、「外国に行ったらその文化に合わせるべき」というちょっとした義務感のようなものを無意識のうちに感じていたのかもしれない。そうであれば、日本にいる外国人にも同じ水準を期待してしまう。本当の意味で文化を受け入れるとは、そういうことではないだろう。

今回のドイツ側参加者のうち半分弱はビーガンまたはベジタリアンだ。しかし私がこれに気付いたのは3日目の夜。それまで既に散々食事を共にしてきたのにと、私はかなり驚いた。日本でもビーガンやベジタリアン専用のレストランは増えてきているものの、どこのレストランにも当然に選択肢がある状況からは程遠い。専用のレストランに行くことを「強要」するのではなく、既存のメニューにオプションを追加するやり方は、人々の選択を容易にする素敵な方法だと感じた。
ビーガンやベジタリアンに対して日独のアプローチに違いが見られる要因は、単純に食文化や絶対数の違いもあろうが、ここでも、日本の「和」の心が少し関係しているように思う。私が思うに、ハーモナイゼーションは、帰属意識と表裏一体だ。調和を重んじるが故に、他の人と同じこと、同じグループに所属していることに安心感を覚える。実際、「和」の心があるからこそ、「日本人は丁寧で礼儀正しい」というイメージにも繋がっていると思う。注意すべきは、多数派の言う「同じグループ」に所属しない人の扱いであろう。少し人と違う選択をすれば、たとえ周囲に悪意が全く無くとも、「特別枠」に落ち着いてしまう。だからこそ私も、「友達がビーガン・ベジタリアンなのであれば、専用のレストランを探さなければ」というマインドに陥りがちなのだろう。本当の意味で人々の選択の自由を重んじ、多様性を受け入れ、包摂する社会であれば、ビーガンやベジタリアンであっても周りが気付かない、というか、もはや気にも留めないのだろうと思う。ベジタリアンのドイツ側参加者に、私は「レストランで私がお肉を食べることについて、何か思う?」と勇気を出して聞いた。彼は、「各人の選択だから、もちろん干渉しないよ」と笑って答えた。各人の多様な選択を容易にすること、そしてその多様性を受け入れ包摂し、決して強要しないこと― その重要性は頭で十分に理解しているつもりだったのだが、参加者との会話の中で、自分の中の「無意識」に気付かされた。折しも、次回の日独ヤングリーダーズ・フォーラムのテーマは、「多様性と包摂」。これから、私は同窓生としてプログラムの内容を検討する立場になる。自身の無意識との対峙を前に、今から胸が高鳴る思いである。

日独を繋ぐ
冒頭に記した、暗く寂しいベルリンのイメージは、私の中にもう無い。驚きと発見、笑いに満ちた10日間は、その一瞬一瞬が貴重で、とても忘れ難いものであった。何よりも、このプログラムを通じ、一生の友人が出来たことは、私にとってかけがえのない宝である。今般得られた学びを胸に、日独「ヤングリーダーズ」の名の通り、将来の日独関係を更なる高みへと押し上げる一助となりたい。両国を繋ぐ架け橋になりたい。他の参加者も、バックグラウンドは違えど、私と同じく意を強くしているものと確信している。
今回、このような貴重な機会を与えて下さった、主催者のベルリン日独センター、スポンサーの大同生命保険、森記念製造技術研究財団、山岡記念財団、ヤンマーホールディングス、ユアサM&B、そして先生方、同窓生、全ての皆様に心より御礼申し上げ、結びに代えさせていただく。